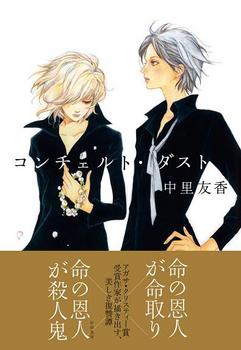行間を読むというのはこういうことだよエリオット [か行]
そうシグモンドも『カンパニュラの銀翼』で言ってました。
(正確には「文間を読むとはそういうことなんだよ、エリオット」)
ポーの『大鴉』に関する考察的な①~の続き。
私は実は、それほどエドガー・アラン・ポーに親しんできたと誇れるものはなく、
留学先の大学の英文学の教本に載っていた
Cask of the Amontilladoについて、
中間試験用の小論を書いて提出したことがあるくらいでした。
今回、文芸作品の翻訳に携わるまで、ポーに関して原文で扱ったのは、
その短編にも満たぬくらいの掌握小説Cask of the Amontilladoだけ。
日本に帰国してからは『アッシャー家の崩壊』(佐々木直次郎翻訳)を、
青空文庫からダウンロードして、これは好きな作品で何度も読んだ。
あとの作品は常識の範囲で知ってはいるけど、通読したことはない、という状態。
日本語でも英語でも、そうまともに読みこんだことはなかった分、
偏った先入観もなく、まっさらな気持ちで深々とポーの文章に真っ向勝負で、潜っていった。
エドガー・アラン・ポーの『大鴉』の行間から私が何を感じとったか、
この作品を訳す上での全体的な色調やトーン(翻訳の方針、出すべき統一感)
隙間から見える景色とは、
端的に言って
「水、水辺」です。
……詩の舞台は、深夜のと或る部屋、暖炉・扉・床・窓辺・机・椅子近辺なのですが。
『大鴉』はざっくり言えば、
あの世とこの世の境目が夜更けに交わるような状況や錯覚を描いていて、
日本的にいうなれば、彼岸と此岸。
実際ポーも、大鴉がどこからどこにやってきたのかを、
nightly shore―
Night’s Plutonian shore
whether tempest tossed thee here ashore
などという語で表している。
彼岸と此岸という意識は、私が勝手に行間から汲み取ったのではなく、
作中でポー自身によって、かなりクリアに言明されているといえるかと。
韻を踏むための技巧のせいもあるとはいえども、
Night’s Plutonian shoreに至っては複数回、出てきます。
又、たとえば扉の上に掛かっている胸像を描写するとき、
placidという、
穏やかな水面を描写するときによく用いられる言葉を出している。
さらには、
as if his soul in that one word he did outpour.
このoutpourという語も、
感情のほとばしりを意味する動詞とはいえ、
水を扱うときの語。
ポーとしても、
水際や水辺といった雰囲気がひたひたと迫るように意識して、
あえて、この手の語を選んで、描いている。
stillness gave no token,
このstillnessも水を思わせますね。
Still water runs deep という諺がすぐ浮かぶ。
(ちなみに私はこの諺が意味深でなんか好き。)
このstillness gave no token,
「水を打ったよう、波風の兆しも見えぬ」
と水を意識して、私は訳しています。
このstillnessという語も『大鴉』の詩で度々、登場します。
詩の最後でも、
僕の浮かばれない影をfloatingという言葉で描写している。
Floatも浮くという、水にまつわる言葉。
逐一、挙げていくときりがない。
作中が、いちいち水を想起させる語で満たされている。
少なくとも私の中では、知らず知らずのうちに、
彼岸と此岸の往来、夜の水際の意識が、
脳内イメージとして蓄積されていたわけです。
訳す当初は、さほど強く意識していたわけではなかったけれども、
なるべく水を意識したいというイメージが、
無自覚のうちに芽生えていたらしい。
推敲する段階ではもう自分でもかなり意識的に、
水辺にこだわって一語一句を選んでいました。
冒頭のWhile I nodded, nearly napping,
「うつらうつらと舟を漕いでいた、まどろみかけていたところ」
うたた寝していた、居眠りしていた、といった系列の表現の中で、
「舟を漕ぐ」という表現をまず選んだ時に、
『大鴉』を訳していく上での雰囲気の方向性が定まったのだった。
あとは、夜の水辺の気配の中から、言葉を掬い上げていく作業。
there came a tapping
「雫のしたたり落つる音」
tapというのはもともと、タップダンスとかのタップ。
カツカツいう音なわけですが、
カツカツ、こんこん、コトコトといった類のオノマトペを安易に使うのは避けたかった。
日本語はオノマトペがかなり特殊というか、豊富にありすぎる。
もとの英語がオノマトペを使っていないので、
「もしもエドガー・アラン・ポーが現在、日本語が母国語になっていて同じ詩を書いたとしても、
絶対このオノマトペを使うと思う!」
と、よほど確信できる、しっくりくる語がない限り、
こと、詩においては、慎重に扱わなくてはいけない、と思っていました。
tapという単語はtap water (水道水)とかのtapでもあります。
やはり液体に関連する語。
tap(タップダンスとかのタップ)とtap(水道水とかのtap)とでは語源が全く異なるので、
はたしてポーがこの同音異義語を意識して、tappingを使ったか――
については、人によって解釈が異なるかもしれませんが、
私は無関係ではないと思った。
私自身が小説を書くときに、同音異義語は時としてかなり意識して用いている。
―隠微と淫靡とか―
―凶器と狂気とか―
―片身と形見とか―
隠微にいやらしい淫靡の意味はないのだが、
そこはかとなくそういったニュアンスを秘めたいときに使う。
凶器を、武器と言わないでわざわざ凶器と書くときには、
使うほうに必ず非があり、その非は、なんらかの狂気を伴うものかもしれない――
という可能性をさりげなく示唆したり、知らず知らずのうちに植えつけたりするときに使います。
なんとなく感じさせる雰囲気を言外に醸し出したいときに、
作家は――少なくとも私という作家は、そういった手法をとることも多い。
片身と形見については、
短編「セイヤク」や「゛極東での若き日々”」で、
実際かなり意識的に使った経験があります。
セイヤクのときには、編者の井上雅彦先生がこの同音異語に、
すぐさまピンと気づいてくださって
「いいですね」とコメントをくださった。
゛極東での若き日々”
においては、担当編集者がむしろ全く気付かず、
「なぜ片身のようなヴァイオリンという言葉を使うのか、単にヴァイオリンで良くないか?」
小説家は書き手のプロ、いっぽう編集者はいわば読み手のプロなので、観点が全く異なるのだ。
(尚、小説家が書き手のプロで、編集者が読み手のプロという、
この認識が双方で食い違うと、仕事をする上でギクシャクしがちだ。)
で、私はここぞとばかりに、かなり熱く、
「ここは片身という語から、形見というイメージを読者にできればそこはかとなく感じてもらいたい。
実際はそうと気づいてもらえずともよい。
知らず知らずのうちに作品の雰囲気にそういう意識を浸透させたい。
そういった意図で、片身という言葉をあえて入れている。
セイヤクという短編では、そこを評価してもらってもいる。そのときのと同じヴァイオリンです!」
と力説して、小説に書いた記憶があります。
小説に限らずとも、日常において語感と語意というのは意外にも作用しあっていると思う。
まったく同音なわけでなくとも、
たとえば「姑息」という言葉を「一時しのぎ」という本来の意味ではなく、
「卑怯な」といったニュアンスで使う、
いわゆる誤用のほうが、現況、7割の日本人に浸透しているらしい。
これは「姑息な」という音の語感が、「こしゃくな」という語感と似ているからでは?
『大鴉』の詩の中でtappingという語に出会ったときに、
私は水や液体のイメージを喚起されつつ、何か打ちつける意味をまっさきに受け取った。
そのニュアンスを的確に表せたら、と思い至ったのが
「雫のしたたり落つる音」
尚、今回、翻訳し終えた後に、
過去の訳者の『大鴉』の詩を二編ほど、探して読んでみました。
いずれも「ほとほとと」という語が用いられていた。
ほとほとは素敵ですが、
原文はthere came a tapping
a tappingなので、1タッピング。
一方「ほとほとと」だと複数回、物音が鳴ってるような感じが強調される。
無論a tappingで「ほとほととした音」1セットと考えることもできるし、
オノマトペは雰囲気音感なので、一回二回とか厳密に数えきれる数量ではないのだが。
betook myself to linking fancy unto fancy
「夢幻の淵へと糸を垂らして爪繰った」
「淵」という語を出さなくても訳せますが、
前述の「舟を漕いでいた」という表現と同様に、
水を意識した「淵」という語を使ったほうが、より水際としての統一感が出ます。
押し寄せてくる彼岸と此岸のせめぎあい、
夜の淵の深みのような気配が、
ムードとして色濃く出るかと。
……と、まぁそんな感じで、終始、行間に、
ひたひたと夜の水辺を感じつつ、訳し終えたわけでした。
『E・A・ポー (ポケットマスターピース09)』
が刊行となったのち、本の編者であり立役者でもある翻訳家の鴻巣友季子氏から
「どのような経緯で、--a tapping--を--雫のしたたり落つる音--
と、中里流に訳すに至ったのか」という質問を戴いた。
「水です」
ちょうどこのブログに書いているようなことを、長々お答えしたところ、
《いいですね。tapと水、水の雫は自然と結びつく》
と、賛同いただけてとても嬉しかった。
《ついでに言うと、rapはlapとも重なる。波がひたひた、のような》
と。
まさに、そうでした! 大鴉の原文は
…napping
…tapping
…rapping
と韻を踏んであって、
rapはラップ音のラップ、連想されるlapは波が打ち寄せる、潮の満ち引きなどをあらわす動詞です。
さらには、
《ガストン・バシュラール「水と夢」にも、ポーにおける水と死と夜についてのimageryについて書かれていた》
とのこと。
……水と死と夜……
なんと私の琴線に触れる語であることよ!
私はガストン・バシュラール「水と夢」という著作を、
恥ずかしながら、まったく知らなかったので、
――読もう!
以来、ひそかに息巻いているのだが、
いまだ実行に移せていません。
(正確には「文間を読むとはそういうことなんだよ、エリオット」)
ポーの『大鴉』に関する考察的な①~の続き。
私は実は、それほどエドガー・アラン・ポーに親しんできたと誇れるものはなく、
留学先の大学の英文学の教本に載っていた
Cask of the Amontilladoについて、
中間試験用の小論を書いて提出したことがあるくらいでした。
今回、文芸作品の翻訳に携わるまで、ポーに関して原文で扱ったのは、
その短編にも満たぬくらいの掌握小説Cask of the Amontilladoだけ。
日本に帰国してからは『アッシャー家の崩壊』(佐々木直次郎翻訳)を、
青空文庫からダウンロードして、これは好きな作品で何度も読んだ。
あとの作品は常識の範囲で知ってはいるけど、通読したことはない、という状態。
日本語でも英語でも、そうまともに読みこんだことはなかった分、
偏った先入観もなく、まっさらな気持ちで深々とポーの文章に真っ向勝負で、潜っていった。
エドガー・アラン・ポーの『大鴉』の行間から私が何を感じとったか、
この作品を訳す上での全体的な色調やトーン(翻訳の方針、出すべき統一感)
隙間から見える景色とは、
端的に言って
「水、水辺」です。
……詩の舞台は、深夜のと或る部屋、暖炉・扉・床・窓辺・机・椅子近辺なのですが。
『大鴉』はざっくり言えば、
あの世とこの世の境目が夜更けに交わるような状況や錯覚を描いていて、
日本的にいうなれば、彼岸と此岸。
実際ポーも、大鴉がどこからどこにやってきたのかを、
nightly shore―
Night’s Plutonian shore
whether tempest tossed thee here ashore
などという語で表している。
彼岸と此岸という意識は、私が勝手に行間から汲み取ったのではなく、
作中でポー自身によって、かなりクリアに言明されているといえるかと。
韻を踏むための技巧のせいもあるとはいえども、
Night’s Plutonian shoreに至っては複数回、出てきます。
又、たとえば扉の上に掛かっている胸像を描写するとき、
placidという、
穏やかな水面を描写するときによく用いられる言葉を出している。
さらには、
as if his soul in that one word he did outpour.
このoutpourという語も、
感情のほとばしりを意味する動詞とはいえ、
水を扱うときの語。
ポーとしても、
水際や水辺といった雰囲気がひたひたと迫るように意識して、
あえて、この手の語を選んで、描いている。
stillness gave no token,
このstillnessも水を思わせますね。
Still water runs deep という諺がすぐ浮かぶ。
(ちなみに私はこの諺が意味深でなんか好き。)
このstillness gave no token,
「水を打ったよう、波風の兆しも見えぬ」
と水を意識して、私は訳しています。
このstillnessという語も『大鴉』の詩で度々、登場します。
詩の最後でも、
僕の浮かばれない影をfloatingという言葉で描写している。
Floatも浮くという、水にまつわる言葉。
逐一、挙げていくときりがない。
作中が、いちいち水を想起させる語で満たされている。
少なくとも私の中では、知らず知らずのうちに、
彼岸と此岸の往来、夜の水際の意識が、
脳内イメージとして蓄積されていたわけです。
訳す当初は、さほど強く意識していたわけではなかったけれども、
なるべく水を意識したいというイメージが、
無自覚のうちに芽生えていたらしい。
推敲する段階ではもう自分でもかなり意識的に、
水辺にこだわって一語一句を選んでいました。
冒頭のWhile I nodded, nearly napping,
「うつらうつらと舟を漕いでいた、まどろみかけていたところ」
うたた寝していた、居眠りしていた、といった系列の表現の中で、
「舟を漕ぐ」という表現をまず選んだ時に、
『大鴉』を訳していく上での雰囲気の方向性が定まったのだった。
あとは、夜の水辺の気配の中から、言葉を掬い上げていく作業。
there came a tapping
「雫のしたたり落つる音」
tapというのはもともと、タップダンスとかのタップ。
カツカツいう音なわけですが、
カツカツ、こんこん、コトコトといった類のオノマトペを安易に使うのは避けたかった。
日本語はオノマトペがかなり特殊というか、豊富にありすぎる。
もとの英語がオノマトペを使っていないので、
「もしもエドガー・アラン・ポーが現在、日本語が母国語になっていて同じ詩を書いたとしても、
絶対このオノマトペを使うと思う!」
と、よほど確信できる、しっくりくる語がない限り、
こと、詩においては、慎重に扱わなくてはいけない、と思っていました。
tapという単語はtap water (水道水)とかのtapでもあります。
やはり液体に関連する語。
tap(タップダンスとかのタップ)とtap(水道水とかのtap)とでは語源が全く異なるので、
はたしてポーがこの同音異義語を意識して、tappingを使ったか――
については、人によって解釈が異なるかもしれませんが、
私は無関係ではないと思った。
私自身が小説を書くときに、同音異義語は時としてかなり意識して用いている。
―隠微と淫靡とか―
―凶器と狂気とか―
―片身と形見とか―
隠微にいやらしい淫靡の意味はないのだが、
そこはかとなくそういったニュアンスを秘めたいときに使う。
凶器を、武器と言わないでわざわざ凶器と書くときには、
使うほうに必ず非があり、その非は、なんらかの狂気を伴うものかもしれない――
という可能性をさりげなく示唆したり、知らず知らずのうちに植えつけたりするときに使います。
なんとなく感じさせる雰囲気を言外に醸し出したいときに、
作家は――少なくとも私という作家は、そういった手法をとることも多い。
片身と形見については、
短編「セイヤク」や「゛極東での若き日々”」で、
実際かなり意識的に使った経験があります。
セイヤクのときには、編者の井上雅彦先生がこの同音異語に、
すぐさまピンと気づいてくださって
「いいですね」とコメントをくださった。
゛極東での若き日々”
においては、担当編集者がむしろ全く気付かず、
「なぜ片身のようなヴァイオリンという言葉を使うのか、単にヴァイオリンで良くないか?」
小説家は書き手のプロ、いっぽう編集者はいわば読み手のプロなので、観点が全く異なるのだ。
(尚、小説家が書き手のプロで、編集者が読み手のプロという、
この認識が双方で食い違うと、仕事をする上でギクシャクしがちだ。)
で、私はここぞとばかりに、かなり熱く、
「ここは片身という語から、形見というイメージを読者にできればそこはかとなく感じてもらいたい。
実際はそうと気づいてもらえずともよい。
知らず知らずのうちに作品の雰囲気にそういう意識を浸透させたい。
そういった意図で、片身という言葉をあえて入れている。
セイヤクという短編では、そこを評価してもらってもいる。そのときのと同じヴァイオリンです!」
と力説して、小説に書いた記憶があります。
小説に限らずとも、日常において語感と語意というのは意外にも作用しあっていると思う。
まったく同音なわけでなくとも、
たとえば「姑息」という言葉を「一時しのぎ」という本来の意味ではなく、
「卑怯な」といったニュアンスで使う、
いわゆる誤用のほうが、現況、7割の日本人に浸透しているらしい。
これは「姑息な」という音の語感が、「こしゃくな」という語感と似ているからでは?
『大鴉』の詩の中でtappingという語に出会ったときに、
私は水や液体のイメージを喚起されつつ、何か打ちつける意味をまっさきに受け取った。
そのニュアンスを的確に表せたら、と思い至ったのが
「雫のしたたり落つる音」
尚、今回、翻訳し終えた後に、
過去の訳者の『大鴉』の詩を二編ほど、探して読んでみました。
いずれも「ほとほとと」という語が用いられていた。
ほとほとは素敵ですが、
原文はthere came a tapping
a tappingなので、1タッピング。
一方「ほとほとと」だと複数回、物音が鳴ってるような感じが強調される。
無論a tappingで「ほとほととした音」1セットと考えることもできるし、
オノマトペは雰囲気音感なので、一回二回とか厳密に数えきれる数量ではないのだが。
betook myself to linking fancy unto fancy
「夢幻の淵へと糸を垂らして爪繰った」
「淵」という語を出さなくても訳せますが、
前述の「舟を漕いでいた」という表現と同様に、
水を意識した「淵」という語を使ったほうが、より水際としての統一感が出ます。
押し寄せてくる彼岸と此岸のせめぎあい、
夜の淵の深みのような気配が、
ムードとして色濃く出るかと。
……と、まぁそんな感じで、終始、行間に、
ひたひたと夜の水辺を感じつつ、訳し終えたわけでした。
『E・A・ポー (ポケットマスターピース09)』
が刊行となったのち、本の編者であり立役者でもある翻訳家の鴻巣友季子氏から
「どのような経緯で、--a tapping--を--雫のしたたり落つる音--
と、中里流に訳すに至ったのか」という質問を戴いた。
「水です」
ちょうどこのブログに書いているようなことを、長々お答えしたところ、
《いいですね。tapと水、水の雫は自然と結びつく》
と、賛同いただけてとても嬉しかった。
《ついでに言うと、rapはlapとも重なる。波がひたひた、のような》
と。
まさに、そうでした! 大鴉の原文は
…napping
…tapping
…rapping
と韻を踏んであって、
rapはラップ音のラップ、連想されるlapは波が打ち寄せる、潮の満ち引きなどをあらわす動詞です。
さらには、
《ガストン・バシュラール「水と夢」にも、ポーにおける水と死と夜についてのimageryについて書かれていた》
とのこと。
……水と死と夜……
なんと私の琴線に触れる語であることよ!
私はガストン・バシュラール「水と夢」という著作を、
恥ずかしながら、まったく知らなかったので、
――読もう!
以来、ひそかに息巻いているのだが、
いまだ実行に移せていません。
2016-10-19 00:14